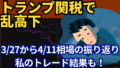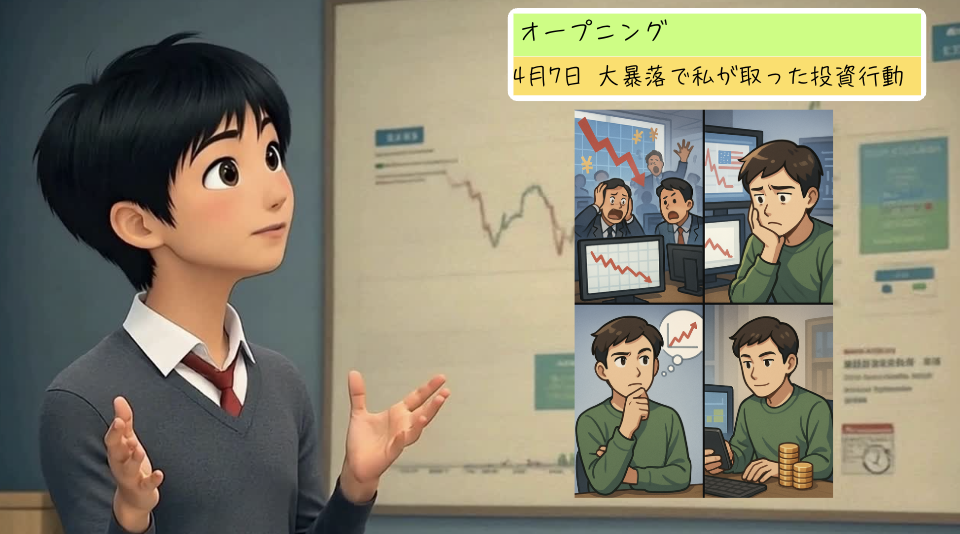
2025年4月7日、日本株市場は「暴落」と形容されるほどの急落に見舞われました。
日経平均は一時3万1,000円を割り込み、TOPIXも年初来安値を更新。米国の関税措置や世界的な貿易摩擦の激化、それに伴う円高進行が重なり、マーケット全体に悲観ムードが広がった一日でした。
リーマンショックの再来なのかと恐れる声もあり、投資家心理は揺れに揺れたと思います。私自身も朝からニュースやチャートを凝視しながら、どこまで下がるのか分からない不安と向き合っていました。
しかし、私は中長期投資を基本としているため、こうした大暴落のときこそ慌てずに「自分の軸を守る」ことが大切だと考えています。
そこで、今日はどのような投資判断をしたのか、具体的な行動や考え方を振り返ってみたいと思います。
暴落の背景
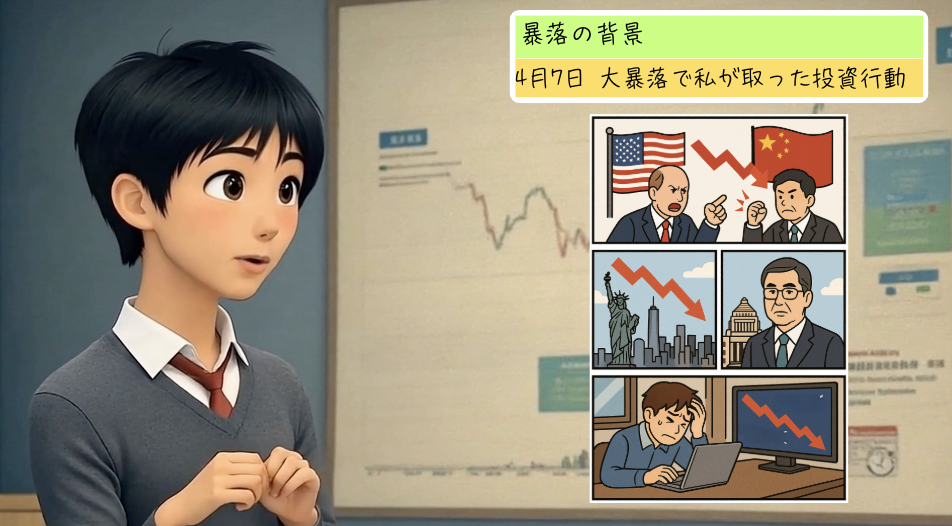
今回の大暴落は、米国の大規模な関税引き上げと、中国をはじめとする各国の報復示唆が大きく影響していると見られています。
世界景気への下押し圧力が一気に高まったことで、米国株も前週末に大幅安となり、その流れが東京市場にも伝播しました。
さらに、石破政権が目立った景気対策を打ち出さず、減税や追加緩和などの政策期待が薄いという国内要因も重なって、不安心理が一段と強まった形です。
寄り付きからのパニック的な売りによって、日経平均とTOPIXは急落し、新興株市場のグロース系銘柄も軒並み投げ売りされるなど、全面安の展開が続きました。
こうした混乱した相場を目の当たりにすると、多くの投資家はリスク回避や追証対応などで資金を引き揚げ、先物を含めた売りがさらに売りを呼ぶ事態に陥りがちです。
現金化を急ぐ動きが広がるのは自然なことですが、私はこういう時期ほど過去のリーマンショックやコロナショックを振り返り、長期目線でどう動くべきかを改めて考えました。
投資アプローチを決めた3つの前提
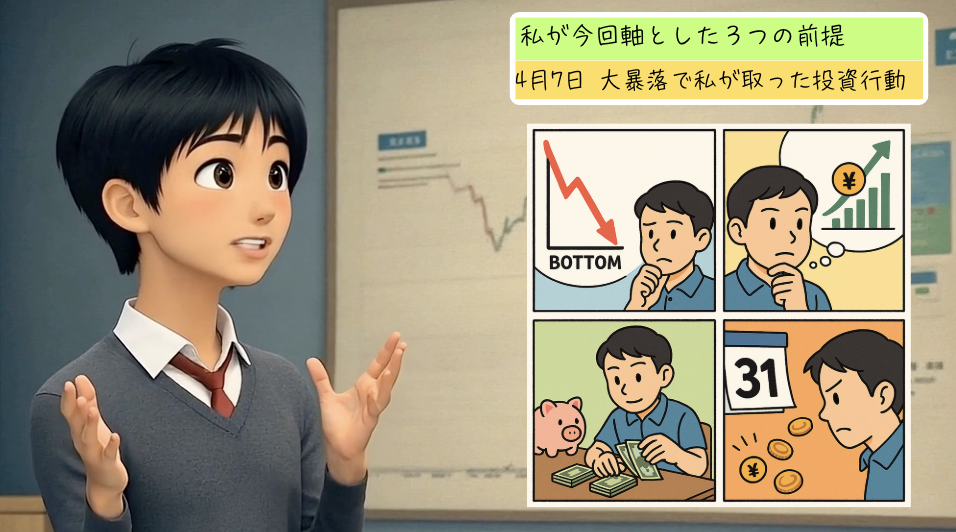
私は今日のような大暴落を前にして、まず三つの前提を意識しました。
第一に、「リーマンショックのときは底を打つまで半年以上かかった」という点です。したがって「ここが一時的な急落の底だ」と決めつけて全力買いするのは危険だと思いました。
第二に、「短期的には下がっても、長期的成長が見込める銘柄はむやみに手放さない」という考え方です。これまで信頼してホールドしてきた企業があるなら、一時的な株価下落に振り回されず、今後5年10年を見据えた成長余地を重視するようにしています。ただし、米国への輸出に関連する銘柄については少し見直しが必要な見解です。
第三に、「あらかじめキャッシュポジションを高めに保つことで、下がったら小刻みに買い増す余裕を持つ」という点です。
昨年末から今年頭にかけて株価がやや過熱気味と感じられた時期に利益を確定していたため、今日の急落局面でも焦らず一部資金を投下することができました。
具体的な行動:内需中心高配当株への買い増し

今回の大暴落では、何をどのくらい買い増すかは非常に悩ましいところでしたが、私はまず配当利回りが4%を超えるまで売り込まれた内需中心、つまり関税の影響が受けづらいと思われ、為替が円高になった時の銘柄に目を向けました。
どんな銘柄もパニック的に売られるときは、一様に株価が下がりやすいものですが、本来の企業価値や安定した需要、さらには成長戦略を持っている企業が割安水準に落ちてくるケースもあると考えています。
そこに小規模ずつ段階的に投資することで、もし明日以降さらに株価が下がったとしても、買い増しして平均取得単価を下げる余地が残せます。
また、高配当株であれば下落中でも配当が見込めるため、長期保有に耐えられるのが大きなメリットです。
買い付け量はあくまでキャッシュ全体の一部にとどめ、今後の追加下落リスクにも備えています。
下がった時に都度フルベットしてしまうと、さらに深い下落に巻き込まれた場合の選択肢が減るため、「もう一段下がっても、もう一回買える」という精神的な余裕を持つように努めました。
指数との付き合い方:グロース250とグロースコアをどう見るか
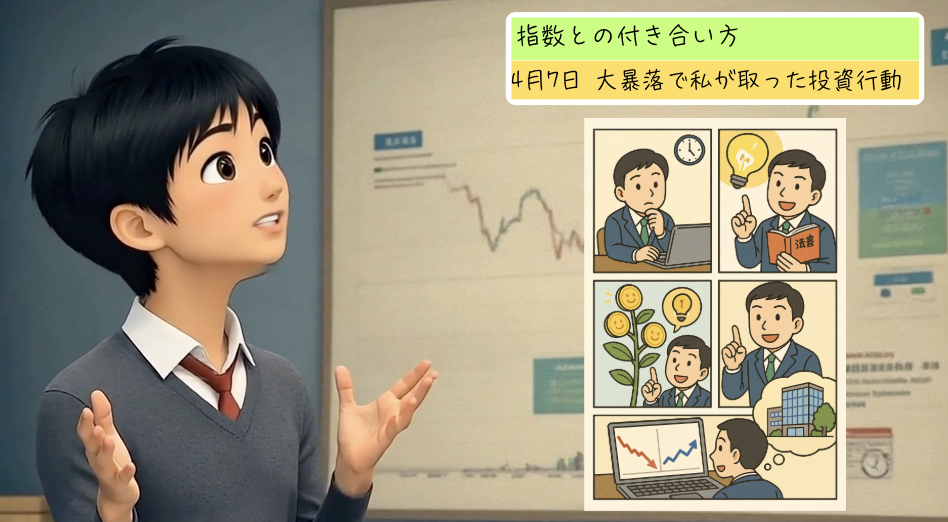
暴落時にはETFなどの指数買いを検討する方も多いですが、私は日経平均やTOPIX、グロース250には手を出しませんでした。
関税の影響を強く受けやすい輸出関連企業が指数に含まれているうえ、グロース250は250銘柄が厳選されているとはいえ、実際にはボラティリティの高い企業が多い印象があるからです。
急落時に真っ先に資金が逃げる可能性を想定し、今は様子見が妥当と考えました。ただ、グロースコア指数については、もしさらに割安になったと感じられるタイミングが訪れるなら投資を検討してみようと思っています。
一方で、すでに保有している少し割高感のあった銘柄を手放すかどうかも悩みどころでしたが、結局私は売却に走らず、今後の動き次第ではむしろ買い増しすることも選択肢に入れる方針です。
長期投資の観点から見れば、強いビジネスモデルや経営戦略を持つ企業ほど、急落局面で取得単価を下げられると、その後のリターンが高まる可能性があるからです。
リーマンショックやコロナショックを振り返ってみても、大混乱の最中に静かに買い進めていた投資家が、その後の回復局面で大きく報われる例を数多く目にしました。
まとめ:不安と希望の間でどう行動するか
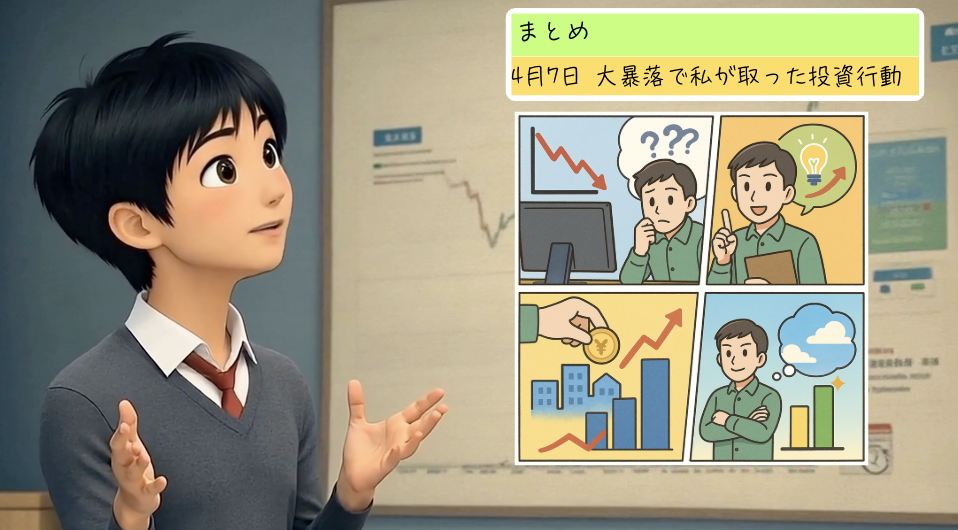
今回の大暴落は、過去の危機と同様に「この先もっと下がるのか、それともここから反発するのか」を誰も正確には断定できない状況だと思います。
実際、私自身も焦りや不安を感じる瞬間はありますが、歴史的に見ればいずれ混乱は落ち着き、新たな相場のサイクルが巡ってくるのが常でした。
だからこそ、どこが底かをピンポイントで当てようとするより、リスク管理をしながら段階的に投資を行う方が現実的ではないでしょうか。
今日の私の行動を簡単にまとめると、「まだまだ下落余地があると考えつつも、内需型高配当銘柄を少しずつ買い増し」「長期成長が期待できる銘柄はホールドを継続」「指数やグロース250は落ち着くまでもう少し様子見」といったところに尽きます。
リーマンショック時も半年以上かけて底を探りましたし、今回も一気に回復するシナリオはあまり期待できません。
けれども、キャッシュポジションに余裕を持たせながら、焦らずコツコツと拾っていけば、将来的に大きく報われるかもしれない。それが私のスタンスです。
どれほど優れたアナリストでも、短期的な市場の動きを完璧に予測することはできないものです。
今はとにかく、上がったらラッキー、下がったらさらに買い増せるといった柔軟な発想で、次の展開を待ちたいと思います。皆さんは今日の市場をどう捉えましたか。
よければコメントなどで意見や感想をお聞かせください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。激動の相場が続きそうですが、慌てず腰を据えて乗り切っていきましょう。
※ 本動画の解説は1例です。投資は自己責任でお願いします。