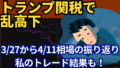皆さん、最近スーパーでの買い物や外食のたびに、「あれ、前より高くない?」と思うこと増えていませんか?

卵も牛乳もお肉も、気づけばじわじわ値上げされていて、財布の中身がどんどん軽くなっていく…。しかも今って、原材料だけでなく“人件費”も高騰してるじゃないですか。飲食店のアルバイト時給が上がったり、社員の賃金が見直されたり、そのコストが商品価格に上乗せされているという話もよく耳にしますよね。
そこで今日は、飲食に関わる人件費がどう価格に影響するか、そしてスーパーや自社製造企業の商品がなぜコスパ良くなるのかを中心に、インフレ時代の食費節約のヒントを探っていきましょう!
背景説明(インフレ&人件費高騰の現状)

まずは全体の背景から。ここ数年、日本は歴史的なインフレ傾向にあります。原材料費はもちろん、電気・ガス代や物流コストなどが上昇し、企業としては何とかして利益を確保しなければなりません。その結果、食品メーカーや飲食店がこぞって値上げラッシュとなり、消費者の家計を圧迫しているわけですね。
さらに近年顕著なのが、人件費の高騰です。人手不足の影響でアルバイトやパートの時給が上がり、大企業でも30年ぶりの大幅賃上げがニュースになりました。企業としては人件費分を何とか売値に転嫁しないといけないので、飲食物の値段も一緒に引き上げざるを得ない。つまり、外食産業や総菜デリなど、人手を多く必要とするサービスほどコストが上がりやすく、結果的に価格が割高になりがちという構図が見えてきます。
飲食における「人件費」の構造とは?
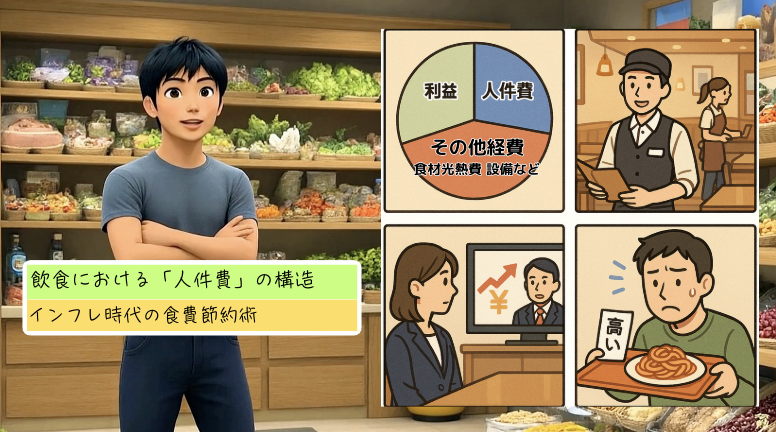
ここでちょっとだけ、飲食産業の“人件費”の仕組みについて触れてみましょう。飲食店の価格をざっくり分解すると、食材原価(材料費)+人件費(スタッフの給与・福利厚生など)+家賃や光熱費などの諸経費+利益という形になります。このうち、人件費の割合は店舗にもよりますが、売上の3割前後を占めることが多いとも言われます。加えて、居酒屋やファミレスなど長時間営業・オペレーションが複雑な業態では、スタッフの人数やシフトの数が多いため人件費がさらに増加しやすい。これがそのままメニュー価格に影響するわけですね。
一方、近年の最低賃金引き上げやアルバイト時給アップなどで、ここ数年で急速に飲食店の人件費負担が大きくなり、特に人手不足エリアだとさらに上乗せが発生します。結果として「外食は割高だな」と感じるケースが増えているのです。もちろん、安全な食材管理や接客サービスを提供するには、一定の人件費は必要不可欠。ただ今はインフレと重なって、「外食の値段が思ったより高い」と感じる人が多いのが現状です。
スーパー vs 自炊:実際どっちがコスパ良い?(人件費の視点付き)

昔から「節約には自炊が一番!」と言われていましたが、今はちょっと事情が変わってきています。なぜなら、スーパーの食材そのものも値上がりしているし、光熱費も高騰中。「材料費もガス代も高い。じゃあ自炊って本当に安いの?」と疑問に思う人も増えているのです。
ただし、飲食店で外食する場合は、先ほど述べたようにスタッフの人件費が価格に乗ってくるため、相対的に割高に感じるケースが多いでしょう。例えば、都心部のファミレスでは、スタッフの時給が1000円〜1200円以上になることも珍しくないので、当然メニュー単価も上がりますし、深夜帯はさらに人件費が跳ね上がります。一食あたりの満足度は高いかもしれませんが、「家計を節約したい」という視点だと、いつも外食というわけにはいかないのも事実です。
一方、自宅で自炊する場合、人件費は“自分の労力”と“時間”です。お金としては直接出ていきませんが、裏を返せば、「自分の労力を時給換算したらどうなる?」という考え方もあります。スーパーで食材を買い、調理をして洗い物をして…結局、1時間〜2時間費やしているなら、その時間に別の仕事をしてお金を稼ぐほうが効率的かもしれません。
こうして考えると、「自炊が必ず安い」わけでもないし、「外食が圧倒的に高い」と切り捨てるのも一概には言えないんですよね。そこに加わるのが「スーパーで出来合いの総菜や惣菜パンを買う」という選択。これは、飲食店ほど大人数のスタッフを常駐させなくても(裏方スタッフを集中配置で済ませたり、工場から直送して並べるだけだったり)、規模の経済でコストを抑えているケースが多く、比較的割安に提供できる仕組みがあります。特に次の章で説明する「自社製造」を取り入れている企業なら、さらに安くなる可能性が高いんです。
自社製造ブランドの強み(人件費・加工コストのカット)

飲食企業でもそうですが、「製造から販売までを自社で一貫して行う」と、人件費や中間マージンをうまくコントロールできる大きな利点があります。普通は、メーカー、卸、小売という流れがあり、それぞれで“加工・包装・物流・販売”に人員が必要です。それに伴う人件費が価格に上乗せされていきます。しかし自社工場を持ち、直接店舗で販売する企業なら、間に挟まる業者や、余分な人件費の発生を大幅にカットできるわけですね。
例えばスーパーのプライベートブランド商品。大手スーパーやドラッグストアでは大量生産したPB商品を全国の店舗に一括配送しているため、食品メーカーのOEM(受託生産)を活用する場合でも、コスト管理や品質基準をスーパー自身が主導で行います。その結果、広告費やブランド料を抑えられ、「メーカー品より少し安いけど十分おいしい」というPB商品が続々登場しているわけです。さらに、業務スーパーのように海外に自社工場を構えて、原料仕入れから加工まで一貫して行うケースでは、中間業者をほとんど通さず、大量生産・大量輸入を実現。これが最終的な消費者向け販売価格の安さに直結しているのです。
要するに、「自社製造」=自社のスタッフに報酬を支払うだけで完結し、外部の人件費に相当する部分は最小化できるという構造があり、ここにコスト優位性が生まれます。人件費が高騰している時代こそ、「他社を挟んで余分な賃金を負担してもらわなくて済む」という点で、自社工場や自社ブランドを持つ企業は値段を抑えやすくなるわけですね。
実例紹介(人件費の要素を補足しつつ)

業務スーパーの激安商品には、神戸物産グループが海外工場などで自社製造したオリジナル商品が多いのが特徴。たとえば冷凍食品やパン類など、「海外の工場で大量に作り、日本へコンテナ輸送→国内でそのまま業務スーパーへ」という流通経路を確立しています。海外拠点のスタッフ雇用コストも含め、事業グループ全体で最適化しているため、中間業者への人件費負担が発生しにくいんです。店頭でも生鮮売り場を最小限にし、惣菜コーナーを設置せずレジスタッフだけで回せるようにしているため、店舗運営コストも低い。結果として消費者に安く提供できるというわけですね。
コストコは会員制にすることで、年会費からの安定収入を確保。そのおかげで、店頭でのマージンは極限まで低くできるというビジネスモデルです。ただ会員制といっても、店舗は倉庫型で広大なフロアに商品をずらっと並べるため、店内で商品を小分けしたり細かく対応したりするスタッフ数は最低限に抑えられます。パレットに乗せたまま陳列される商品も多く、陳列用スタッフも少ない。加えて、大容量でのまとめ売りに特化しているため、1単位あたりのスタッフ稼働は意外と少なく済むわけですね。
消費者目線での賢い選択(人件費まで考えると?)

インフレ時代の食費節約は、原材料だけでなく「人件費コストがどう乗っているか」まで見極めると、より納得感のある判断ができます。特に外食には調理スタッフ・サービススタッフなど多くの人件費が含まれますから、どうしても割高に映りやすい。一方、スーパーやPB商品、自社加工品は人件費のかかり方が異なるため、値段が抑えられやすいわけです。
そこで以下のアプローチをおすすめします。
外食を減らし、スーパーやテイクアウト総菜を活用
飲食店でフルサービスを受けると、そのスタッフコストが確実に価格に反映されます。忙しい日は外食でリフレッシュするのも良いですが、頻度を抑えるだけで月の食費はだいぶ変わるはずです。代わりにスーパー総菜などの“中食”を上手に使えば、外食ほど人件費が高くないぶん、割安でそこそこ美味しいものが手に入ります。
プライベートブランドや自社製造商品を優先的にチェック
お店独自のPB商品の多くは、広告費や中間マージンが抑えられ、さらに製造や加工の段階でも“外部”の人件費が加算されにくい構造があります。メーカー品と比べて「ちょっと安いな?」と感じたら、とりあえず試してみる価値アリ。品質が合えば大きな節約になります。
量が多いほど単価が下がる(スケールメリット)
たくさん作り、たくさん売る企業ほど固定人件費が薄まるので、価格を下げやすくなります。業務スーパーやコストコのような大量販売型店舗を活用すれば、そのメリットを享受しやすい。自分だけでは消費しきれなくても、友人とシェアしたり冷凍保存したりすれば、結果的に安く済むケースが多いですよ。
自炊する場合は「自分の時間コスト」とバランスを取る
自炊にかかる“自分の労力”を過小評価しすぎると、時間を無駄にして本末転倒になることも。とくに忙しい平日はスーパーのお惣菜やPB商品に頼って、休日にまとめて作り置きするなど、自分の“人件費”も考慮したハイブリッド戦略が心身の健康にも家計にも良いバランスです。
まとめとエンディング

インフレと人件費高騰が重なる今の日本では、外食価格がますます高く見えるのは当然と言えるかもしれません。かといって「全部自炊!」と突っ走っても、時間と労力をかけすぎて疲れ果てるなんてことも…。そんなときこそ、「飲食店がどれくらい人手をかけているか」「どれだけ自社製造やPB商品で人件費を最適化しているか」を見極めれば、節約のヒントが見つかります。
結局、インフレには「お得情報や構造を知っている人が勝つ」んですよね。業務スーパーやコストコなど、自社製造や大量生産の恩恵をダイレクトに受けられる場所を活用して賢い消費をする。外食も、「ここはスタッフが多いフルサービス店だから、贅沢したい日に行こう」なんて感じでメリハリをつけると良いでしょう。あなた自身もある意味“労働力”を持つ一つの企業のように、自分の時間やコストを最適配分していければ、インフレだって怖くない…はず!
というわけで、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。これで皆さんも、人件費の高騰がもたらす価格上昇の仕組みが少しクリアになったのではないでしょうか?次回の動画では、さらに具体的な「お得術」や「時短テクニック」などもご紹介予定ですので、お楽しみに!それではまた~!